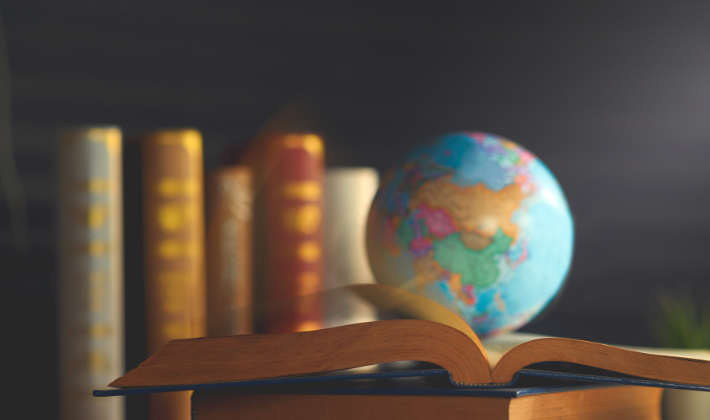こんにちは!つむぎです。
今日は、「哲学」をテーマに書いてみたいと思います。
私たちはドラマなどを見ていると、知らず知らずのうちに“理想の生活”というイメージが出来上がってしまいます。
ドラマの主人公が、あり得ないほど広い部屋に住んでいて、ブランドの洋服やバッグを身につけ、毎日のように高級レストランで食事をしている。
その職業の給料では到底無理だろうと思っても、「これが大人の当たり前なんだ」と刷り込まれてしまう。
雑誌やSNSでも同じです。「女性」「30代」「社会人」であれば、正社員、一定の年収、結婚、子ども、持ち家、車、素敵な持ち物…といった“標準パッケージ”が提示される。
気がつけば、そんな価値観に侵食されて「私は遅れているのでは」「私には足りないものが多いのでは」と焦りや不安を感じてしまうこと、ありませんか?
私も20代まではそうでした。もともと持っていなかった欲が駆り立てられ、「あれが欲しい」「これも必要かも」と思い込んで、現状に不満を持つ。
そんなときに助けになったのが、“哲学する”ことでした。
もしあなたも思い当たることがあるなら、今日のお話が少しでも視点を変えるヒントになれば嬉しいです。
そして、このブログが、あなたの人生をより豊かにするきっかけになれば幸いです。
「哲学」とは、問いかけ考えること
「哲学」と聞くと、難しくて堅苦しい学問を思い浮かべるかもしれません。でも本来の哲学は、特別な知識をひけらかすものではなく、「問いかけ考えること」。
たとえばテレビやSNSで流れてくる価値観に対して、「本当にこれが正しいの?」「これが“普通”って誰が決めたの?」と疑問を持つこと。
普通なんてないし、みんな同じなんてありえない。周りがどうかではなく、「私にとっての当たり前は何だろう」と考えること。それが哲学する、ということの第一歩だと思うのです。
哲学を知ることで、自分の思考や価値観の幅がぐっと広がります。そして、疲れたときこそ、一旦立ち止まり、欲や焦りに飲み込まれる前に、自分の声に耳を傾けるきっかけになります。
西洋哲学と東洋哲学―ふたつの入り口
哲学には大きく「西洋哲学」と「東洋哲学」というふたつの入り口があることを、ぜひ知ってほしいです。
ここをごっちゃにして、いきなり有名な哲学者の本を読むと、背景がわからないので、「哲学っていまいちよくわからない...」で終わってしまうと思うからです。
私は西洋と東洋のどちらが正しい・優れているということではなく、色々な考え方・視点があることを知ることが、哲学を学ぶ一番の収穫だと感じています。
なぜなら、正解があるわけではないから。どの哲学者もその時代に考えに考え抜いた“自分なりの真理”を残しているからこそ価値があると思うからです。
西洋哲学(階段型)
- 「まだ真理に到達していない」という前提
- 論理や議論を積み重ね、次世代が前世代の論理を疑い、破壊し、更新していく
- ソクラテスやプラトンなどが代表的
- 歴史に沿って順番に学べば理解できる
東洋哲学(ピラミッド型)
- 「すでに真理に到達した」という前提
- 言葉ではなく、体験することで理解するもの
- 釈迦の悟り、老子の「道(タオ)」などが代表的
- 根拠や過程は明かされず、後世の人が解釈を重ねる
- 学びというより、体験の中で腑に落ちるもの
スタート地点が全く違うので、同じ“哲学”でもアプローチが大きく異なります。でも、その多様な視点を知ることが、自分の世界を広げるヒントになります。
哲学が教えてくれること
哲学を学ぶと、世の中の常識や“当たり前”は、絶対的なものではないことに気づきます。
たとえばコロナ禍。
コロナ前は、接客業でマスクをしたままだったら無礼とされていましたが、コロナ禍以降はマナーになりました。
多くの会社で毎日出勤することが当たり前でしたが、いまはリモートワークが一般的になり、地方移住の需要も増えました。
かつての“常識”は、わずか数年でガラッと変わるものだと実感した人は多いのではないでしょうか。
これまで“事実”や“真実”と言われてきたことも、一つの視点に過ぎない。また時代や国によって“真実”とされることは変わるし、法律やルールでさえ、その時代のその国の人たちが決めたことに過ぎない。
もちろん、法律やマナーはその国で生活する上で守るべきものだと思います。でも、人に迷惑をかけない範囲で、自分が心地よいこと・楽しいことを選んで生きる分には、何の問題もないはず。
であれば、とことん哲学し続け、自分にとっての最善を見つけることこそが、豊かな人生を生きる上で必須のスキルなのではないかと思います。
“哲学する”を日常に取り入れるシンプルな方法
- 疑問を持つ:ニュースやSNSの情報に「本当にそう?」と問いかけてみる
- 書き出す:ノートに“今の気持ち”や“疑問”を書き出してみる
- 本から入る:哲学の入り口になる本を読んでみる
特に最初の一冊としておすすめなのが、飲茶さんの『史上最強の哲学入門』。
体系的でとてもわかりやすく、面白い内容なので、西洋哲学の流れを“階段をのぼるように”スッと理解できます。「哲学って案外おもしろい」と思えるはずです。
その後、続編で「東洋哲学」もあるので合わせて読むと、より哲学の全容を知ることができるはずです。
Audibleでも聴くことができますので、ぜひ気軽に試してみてください。
疲れたときこそ、自分に問いかけてみよう
哲学は正解を押しつけるものではなく、視点を増やしてくれるもの。
「ああでもない」「こうでもない」と考えること自体に価値があると思うのです。
常識や他人の価値観に揺さぶられて迷ったときや疲れてしまったときこそ、“哲学する”時間を持って、自分の本当の気持ちに耳を傾けてみてください。
その小さな習慣が、あなたの人生をもっと豊かに、もっと軽やかにしてくれるはずです。